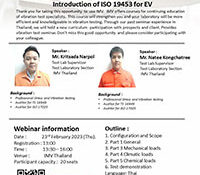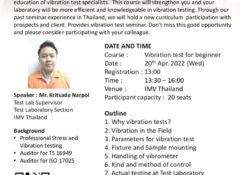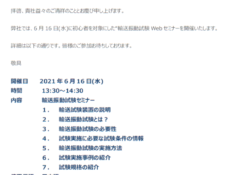IMV Corporation เป็นบริษัทชั้นนำด้านการทดสอบและการวัดการสั่นสะเทือน
ยินดีต้อนรับสู่ไอเอ็มวี
เราเป็นผู้ติดต่อของคุณสำหรับระบบจำลองสภาพแวดล้อมและทดสอบการสั่นสะเทือน
เรานำเสนอเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยปัจจัย ECO: ด้วยระบบของเรา พลังงานและการปล่อย CO2 จะลดลงอย่างมาก เนื่องจากสามารถควบคุมพัดลม
ความเร็ว และการจ่ายภาคสนามได้ โดยขึ้นอยู่กับโหลด เครื่องทดสอบแรงสั่นสะเทือนด้วยนิ้วหัวแม่มือสีเขียว!
การบริการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา